住職は何をしてたのかと、しかられそうな内容です。
以前はほぼ長男が喪主であり、お墓も長男が引き継ぎました。
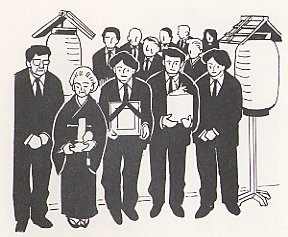
しかし、時代の流れは大きく変わってきています。当寺ばかりではありません。
わずかですが、喪主が誰なのか、お墓の跡取りが誰になるのか、なかなか決まらないこともあります。
「お墓を放棄します」と電話があったきりで、連絡先も分からなくなったこともありました。その後、両親の火葬も後見人さん任せで、一切顔を出さなかったそうです。お骨はどこへ行ったのでしょう。
高齢の入院中の母親が喪主を務め、喪主挨拶の時、「入院中の母に代わり、長男の○○がご挨拶させていただきます。」だけでなく、お墓も放棄状態になったこともあります。
現在は嫁ぎ先のお墓のある娘さんが、取りあえず後を継いでいます。
少子化、子供が娘ばかり、子供がいない、結婚していない、親子が遠く離れて生活している、などだけが原因ではありません。
生き方の意識の違いかもしれませんが、親も子供もいずれ死を迎えることを意識しないでいたことも原因の気がします。
喪主をやるからには葬儀、供養は自分の思いのままやる。霊園も寺墓地も同じと考えていた人も複数いました。檀家を辞めた家もあります。
ある時、ご親戚から通夜の30分前に、本家より遙か高い位の戒名なのは何故かと電話がありました。
葬儀社と何宗でもする坊さん(?)をネットで依頼していたのです。
本家(当寺檀家)や奥さんの兄弟からも意見され、翌日には私が葬儀を勤めました。
男子が家を継ぎながらお墓は継がず、娘夫婦が墓を継いたこともありました。
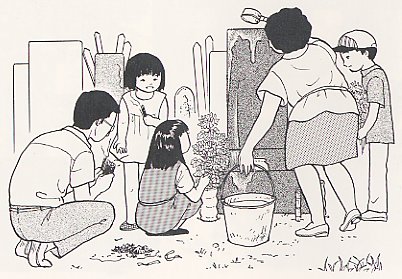
以前ある葬儀屋さんに聞くと、お葬式を行わない家が増えたそうです。
都営団地近くでは、火葬だけが九割と言っていました。
下町でも四割程度しか葬儀をしないそうです。
ある宗教学者の書いた「お葬式は要らない」以降の流れがすごいようです。
なお、「月刊 住職」の記事によれば、この本は仕事の無くなった著者が、他の題名だったのを出版社の言われた題名に沿って書き直した本だそうです。
著者はオーム真理教の身方をして、サリン事件後マスコミから相手にされなくなった人です。
「月刊 住職」に記事を書かせてもらいながら、より金になった方が得と思ったのかもしれません。本人に取材しての記事でした。
現在各地の寺院墓地、霊園も申し込みが極端に減っています。
子供が遠方のため、お墓を移す檀家も年々増えています。
私が住職をするお寺はまだ良い方ですが、地方のお寺さんは、存亡の危機を迎えています。
50年後にはお寺の数が、半分になると言われています。実際地方では深刻な状態になっています。
お寺や神社も安穏としている時代ではないのです。



