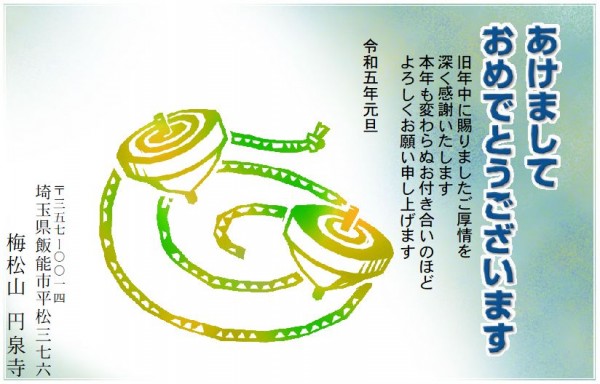青梅信用金庫飯能支店の駐車場に車を止めると、道を挟んで西側に蕎麦・うどん「くりはら」がありました。 かつて不動屋さんのあった場所です。 青信で振り込みを済ますと遅い昼飯としました。 車が丁度出払ったばかりで…
2023年01月
神像 神社・神道の美術
神像 男神像 上の御神像は最近迎えました。底部に元和4(1618)年と書かれています。二代将軍・徳川秀忠の時代です。 骨董屋さんに聞くと、秩父から仕入れたと話していました。 女神像 現在…
平松天神社 1月21日 大祓を行いました。
春日地蔵曼荼羅中の地蔵菩薩? 春日大社 奈良市
日本の美術№67「神道美術」影山春樹編を読んでいると、この地蔵菩薩イラスト像とほぼ同じ図が出てきました。 「春日地蔵曼荼羅」です。 少し異なりますが、奈良国立博物館蔵の春日地蔵曼荼羅がありました。奈良国立博物館link …
上野の森美術館「兵馬俑と古代中国」 台東区上野公園
2015年から16年に東京国立博物館で「始皇帝と大兵馬俑」展が開かれていました。 今回は近くの上野の森美術館で「兵馬俑と古代中国」展です。 兵馬俑は撮影可能でしたので、拝観者の殆どがスマホで撮影していま…
東京国立博物館 国宝「長谷川等伯筆 松林図屏風」 日本文化のひろば
今年は博物館が創立され150年になります。さらに戦後、国立博物館となりました。 国立博物館となり、最初に納められたのが、長谷川等伯筆の松林図屏風です。 ※午前中はサントリー美術館で智積院蔵長谷川等伯の国宝・…
水仙が咲き出しました。
兎の木目込み人形が奉納されました。
毎年お正月には檀家さんから十二支に因んだ木目込み人形が奉納されます。 今年は卯年ですので兎さんです。 亀が乗っています。 ウサギとカメの話しを誰もが浮かべるでしょう。  …
あけまして おめでとうございます
今年も武蔵野七福神・福禄寿さまの御開帳を御本堂にて元旦より十五日間行います。円泉寺は11日から1月末頃までは阿弥陀堂。 布袋尊 山口観音 埼玉県所沢市上山口2203 地図 04-2922-4258 事務局 …