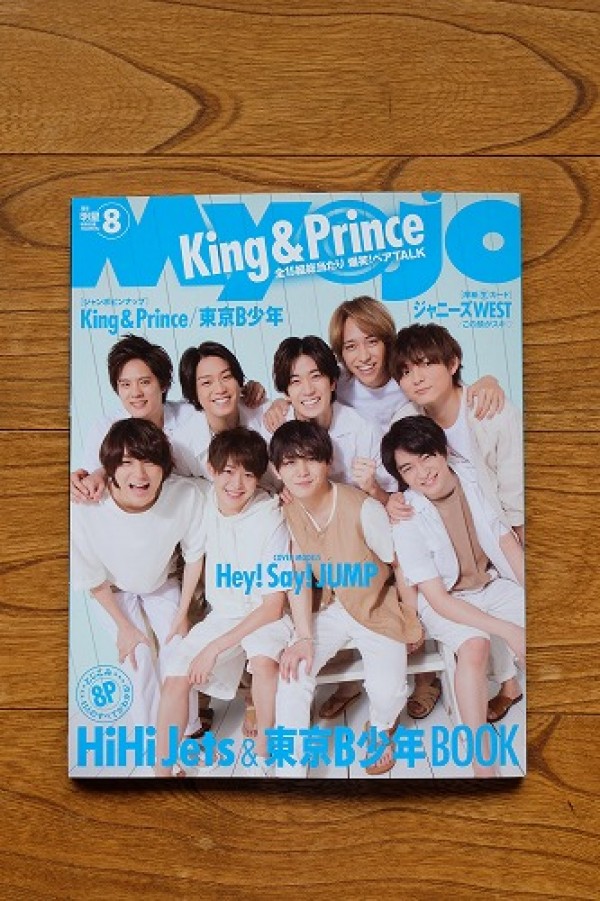タイムズマートの本部は、とうになくなっているのですが、タイムズマート飯能の店長さんは年中無休で、まだ頑張っています。 埼玉県飯能市山手町16-6 グリーンビル1F 場所 ユーチューブ それだ…
2018年06月
天神社宮司が日刊明星に俳優さんの滝行指導で掲載されています
西澤宮司は月に数回はマスコミからの取材や、タレントさんの滝行撮影、海外メディアの撮影などを受けています。 地元の方々の応援も後押ししていただいています。檜原村観光協会のご協力もいただけることになりました。 …
箭弓稲荷神社参拝 埼玉県東松山市
東松山市の箭弓稲荷神社に参拝して参りました。 かつて東松山駅には西口がありませんでしたが、西口ができ電車での参拝には便利になっています。東口には、赤い大きな鳥居がありましたが、老巧化と再開発のためになくなっていました。 …
トンボ
境内にはいろいろな昆虫がいます。 クマンバチ、アシナガバチは願い下げですが、蝶やトンボが飛んでいました。 これはオニヤンマだと思います。 やっと止まっているトンボを撮ることが出来ました。同じトンボです。 …
梅干し
境内の石屋さんが、梅を漬けています。40キロは漬けているようです。 ほとんどを檀家さんや信者さんに分けているようです。 私の家には、数十年分の梅干しがありますが、お医者さまから塩分控えめと言われておりますので、なめる程度…
沙羅の花
境内の沙羅の花は、これから咲く花、咲いている花、実とかわっていきました。 まだ蕾です。 花が開きました。 花びらが落ちて、実となります。 実には、雄しべがありました。 実が枯…
洋服に下駄? 僧侶と下駄
何とも変な題で、申し訳ありません。 別々に取り上げても良いのですが、時代の変遷を感じています。 先日、ある女性とショートメールで連絡を取っていると、会話の流れで会社に下駄で出勤したと書いてありました。 「洋服 下…
香取神宮参拝 千葉県香取市
前回お参りに来たときより、かなり多くお参りに来られているようです。 三の鳥居と総門から、本社に向かいます。 夏越の祓のため、茅の輪くぐりをする人が沢山いました。 インターチェンジから近いからでしょう。東国三…
息栖神社参拝 茨城県神栖市
鹿島神宮の後に息栖神社をお参りしました。 駐車場に駐めると、先ずは忍潮井に向かいました。 伊勢の明星井、山城の直井と並び日本三霊泉と呼ばれています。 忍潮井(おしおい)の内 女瓶 東国三社…
鹿島神宮参拝 茨城県鹿島市
仲間に鹿島神宮などの話をすると、日時を合わせ5人で東国三社にお参りに行くことに致しました。 先ずは、鹿島神宮参拝です。 鹿島神宮 …